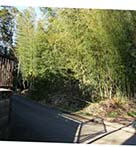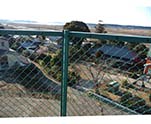2014年2〜3月、雪と梅を交えつつ「藤ヶ谷城跡」「手賀城跡」。
そして、いよいよ春旅行「茨城北部編」始まり始まり〜!
| 今回は前半が日常編、後半から「茨城北部編」に突入〜(^O^)<ヤンヤ・ヤンヤ♪ まずは日常編、前回の最後にチラと写真を出した柏市の「藤ヶ谷城跡」、その後は2月に雪がいっぱい積もり、3月に梅の花が咲いた風景を経て、旅行直前に行った「手賀城跡」(興福院と大杉神社の崖)をお届け〜♪ そして、いよいよ「茨城北部編」に入る。 今回は一日目……残念ながら雨だったが(>_<)、まずは水戸に到着。博物館でじっくりお勉強をしてから、海沿い方面に移動する途中で次回に譲る。 今回まだ日常編やるんで、例の「前連載レポの宣伝」を一度貼ったんだけど、今回は文章も多いし、「茨城北部編」に入るんで外したよ(笑)。 ■2014年2月〜3月・千葉県柏市(・白井市)・松戸市 <柏市・藤ヶ谷城跡(と高柳城跡)> 場所は、16号線の「藤ヶ谷」交差点(地図)に向かって、280号線(地図)から入って行く道沿いからも見えるし、ちょっと右に入れる所もあって(↑この写真がそう)、そこから歩いて行く事もできる。 地図はね……ヤフーやグーグルだと、ちゃんと「藤ヶ谷」や「280号線」と書いてあるんだけど、マップファンはあまり詳しく書いてない(-_-;)。。でもヤフーはすぐアドレス変えるし、グーグルはメチャメチャ便利なんだけど、公開と非公開でアドレスに差があるのかワカラン(それだと提示する気になれない)から、仕方なくマップファンでいこう(笑)。 「藤ヶ谷城跡」は、1395年ごろまでは、田の数などを記す注進状案に地名が見られ、相馬氏の支族・相馬岡田氏の支配が確認できるそうだ。 <相馬氏、下総・陸奥・岡田の分かれ目まで> ┌良将−将門……師国=師常−義胤┬胤綱−胤村┬胤氏 ┌胤康−胤家−胤重 | ↑ | (岡田)├胤顕−胤盛┴長胤−孫駔丸 └良文−忠頼……常胤┬師常 | (陸奥)└師胤−重胤┬親胤−胤頼−憲胤 └(千葉氏) └胤継(下総北相馬郡) └光胤 胤家−胤重(以後→)−胤繁−胤久−胤行−信胤−基胤−義胤−茂胤−直胤 相馬氏系図←詳しくはこちらを まずは、16号線に向かって280号線から入って行く道の風景から↓ →こう進んでいる。道の左にも森が見える(パノラマ3枚ほぼ180度)
この1300年代という時代の相馬氏の様相を見ると、相馬氏は、下総国では南朝勢力に加担の色合いが濃く感じられるが、戦国期に有名な陸奥の相馬氏は北朝勢力である。(2009年5月号) これは惣領家に、支族が反発的立場を取るという、鎌倉期に特徴的な対立関係が芽生えた時代に、南北朝争乱が重なったからと見られている。 藤ヶ谷城に見える相馬岡田氏はどうかと言うと、1336年に小高城(陸奥相馬)に立て籠り、北畠顕家の攻撃を防ぐ戦いで、光胤(陸奥相馬)と長胤(相馬岡田)が討死するなど、ともに北朝側(足利側というべきか)としての連携を思わせる軍事行動をとっている。 それゆえ、「将軍家御計」によって所領安堵を受けており、ここに「長胤の子・孫駔丸」「胤治の子・竹駔丸」「成胤の子・福寿丸」(胤治・成胤は、長胤の弟たちではないかと思う)という幼い後継者たちの名が続く。(幼少ゆえ、実際には長胤の後家となった尼が差配したようである) ただ、このあたりの時代の記録を最後に、その後の相馬岡田氏の現地における動向は不明となっていく。 前に高柳城(善龍寺)などでも言った通り、相馬氏による周辺支配は、質入れなどで失われていったようで、この地域の領主たりえた形跡は伺えなくなる。 (しかし↑系図に見る通り、別の流れから出た「下総相馬氏」は、戦国期、下総北部(茨城南西部)の守谷を中心に名を顕してくる(2009年7月<北東部「守谷城跡」1、城内地区>以降))
その場合、この地域に「相馬」の苗字が多い事から、この「藤ヶ谷氏」じたい、相馬岡田氏の子孫である可能性も考えられるそうだ。 この地域に相馬氏ゆかりの人々が住み続けていたらしい事は、江戸期からも伺える。 江戸時代、川を挟んで対岸の富塚との間に不思議な伝説が起きて、少なくても、この地における相馬氏への思い入れのような物を感じさせられる。 話はこうだ。 「小田原の戦いで、海東(かいどう)八郎延高が南相馬の平胤吉の軍勢に滅ぼされた。 延高の子、村雨丸・延乗は仇討の旅に出て、重病になり、芦椛(ろか)橋で動けなくなった。 (芦椛橋とは、このスグ近くで、前にレポした「矢の橋」(バス停・地図)がある所) 村雨丸は守り神の如意輪観音像を枕元に置き、父の仇討を祈願すると、夢に観音があらわれ、「自分を腹中に納めた聖徳太子像を作って人々に拝ませなさい」と言い、祈願成就と商売繁盛を約束した。 さっきの道の右、工場の所を入って来た(パノラマ4枚180度以上)
(↑工場と民家の間に、左に入る農道がある) 太子像を作ると、村雨丸は力尽きて気を失う。そこに、小田原の戦いに破れて故郷に帰る武士の一団が通りかかり、大将が声をかけた。 村雨丸が事情を話すと、大将は「自分がその仇の者(平胤吉)だ。喜んで斬られよう」と言った。 村雨丸は、その言葉を聞いて、「恨みの気持は消えました」と、笑って橋の下の川に飛び込んで死んでしまった。 残された守り袋には、「平貞盛の子孫」と書かれていた。 平胤吉はその後、僧になり、「善真」と名を改め、村雨丸の墓を建てて、近くの中台に住んで墓守をし、海東父子に法華経を二部、書写奉納した。 その場所が、「村雨山」「二部山」と伝わっている。 里人たちが仮のお堂を建てて聖徳太子像を安置した。やがて人が多くなって富塚村ができると、1593年6月に寺が建ち、「急雨山延乗院」と呼ばれ、今は「急雨山圓乗院西輪寺」と伝わる。 農道の真正面にある森が「藤ヶ谷城跡」の一部かと(^^ゞ(パノラマ4枚180度以上)
1656〜60年には、再建者に大利益があって大成功し、火事盗難にも合わなかった。 洪水がおこると、布川村(茨城県利根町)の聖徳太子像が、西輪寺の太子像を慕って流れ着いた。 そこで太子田と呼んで、太子堂を建て、大下にも堂を作って、二つの太子堂ができた」 以上である。 この伝説に登場する「平胤吉」は、その名と「小田原の戦い」なる事象から、「高城胤吉(戦国期の高城氏当主)では(^_^;)」と思ってしまうが(笑)、どうもこれが、「南相馬」とハッキリ言われてる点、この「富塚」に伝わる点から、富塚のすぐ隣の藤ヶ谷にいた、「相馬氏(相馬岡田氏)」と見れる……という事ではないかと思う。 もう一方の「村雨丸=海東延乗」というのは、すると誰なのか。「貞盛の子孫」というと、常陸平氏のいずれかを指すのでは、と思うが……(^_^;)。。 「村雨丸が誰か」の詮索は一先ず置いて( ^^)//、ここで肝心なのは、「相馬氏の人物が、藤ヶ谷ではなく、その隣の富塚にゆかりの寺を建てる」という点らしいので、注目してみよう。
この「村雨丸」の伝説のある地域は、西に柏市(今いる藤ヶ谷城は柏市)、東に白井市が(一方、富塚城というのが白井市に)あり、この柏市と白井市は、昔も「南相馬」と「印西」という、各々別の領域であったので、原則的にその領域を越えた伝説が存在する事は考えにくい……という点をまず飲み込む必要がある。 ……と言っても、現在この地域を車で走ると、「え、そぉ(^_^;)ゞ?」と意外に思えてしまう程、柏市と白井市の間に、際立った風景の違いなど無い。だだっ広い平野を、いともスンナリ境界を越えて行き来できる(笑)。 ただ、その間のちょうど市境には、さらに北の下手賀沼に続く川が流れている。 強いて言うなら、この川が昔はもっと深い谷をなして、富塚と藤ヶ谷の間を鋭く隔てていたのかもしれない。
↑16号線と280号線の交差点「藤ヶ谷」(地図)を中心に、その東西南北に城地があった事が推測されているが、それらの遺構は殆ど失われている。 しかし昔のこの辺りには、「斬られ庚申」や「矢の橋」「火炎不動」「狐火」などの怪談が多かった。 「斬られ庚申」は、火の玉と怨霊の気配に刀で対抗した商人の話で、実際に刀傷の残る庚申塔がある。 「狐火」や「火炎不動」も火の玉の延長線だが、火炎不動の方は「矢の橋」(地図)とも関連する。 すなわち、藤ヶ谷城と富塚城(地図)の間に戦闘があって(城跡はあるが、「合戦があった」と示す史料はナイ(^_^;))、「矢が川底に溜まって橋になるほど飛び交った」、「落城の炎に浮かんだ勇者のシルエットが不動のようであった」など、合戦伝説に彩られている。(2013年11月<藤ヶ谷、伝説の合戦場跡「矢の橋」>) 合戦話が生まれた背景については後に書くとして、まず怪談が生まれた原因は、夜通るのが怖い場所だった事が考えられる。
律令の始まった頃までは、竪穴式住居だとか古い寺社の痕跡が少なくないが、奈良時代の終わり頃から平安時代の全般にかけて、人の多くいた形跡が乏しくなる。 700年代〜1100年代にかけて、飢饉や地震災害なども多かった。 しかし、それにも増して、人的災害が非常に多い地域だった。 遠国と言われ、京都からは遠いにも関わらず、運脚等の負担の多い国で、日本でも早くから太宰府や陸奥の防人・柵造営の労力に駆り出された地域であった。 さらに蝦夷鎮圧のたび兵を徴収された。連れ込まれた俘囚の起こす叛乱は頻発し、治安は悪く、恐らくはそうした土壌が弊害ともなって、平将門の乱(2008年8月<史跡と順路について(@テキトー画像:笑)>以降、9月号・10月号)、平維良の乱、平忠常の乱(2009年8月号)などが相次ぎ、「亡国」「亡弊国」とまで言われた。 ←こっち方向に森が深まっていく(パノラマ6枚180度以上)
それでも南相馬(こちら柏市がわ)の方は、千葉氏が出て以降は、相馬氏の分家・相馬岡田家の領地として開発されていくようになった事が想像できる。 対して、特に白井市は、国衙領などの区分けでいうと、国衙領同志の「狭間」に位置したと見られている。 上総広常の弟、相馬常清(角田氏の祖)の領に鳥見神社が多いという話も見なくはないが、後続史料に欠くため明確な点は不明である。 市の周りは、北からは下手賀沼、東からは印旛沼の両方から水域が伸びて、水辺に広く囲まれ、昭和になる前までは林業の盛んな、巨木の生え連なる山だった事は、前々回の「神々廻城」レポで伝えた通りだ。(2014年4月②<白井市「神々廻城跡」(鳥見神社)>内) 平安期、集落のあった形跡が殆ど無い中で、注目するのは、群れから孤立した住居跡が見つかっている事だ。 山において一定の季節だけ使う作業小屋という風情のようだ。 それもよく見ると、開けた方向に出入り口を設けないなど、何か人目を避けて生活してる住居跡が多いという。 「国衙の狭間」(つまりハズレ地)という状況と合わせると、律令の制度から弾かれてしまった人々が、国家や国衙を避け、山に隠れ潜む様子などを想像する。 平将門の生涯をドラマ化した「風と雲と虹と」では、このような人々を「うかれ人」(税や労役の負担から逃れて流浪し、役人などに追われる者)として描いていた。
ところが江戸時代になると、慶安年間(1648〜51)に銚子漁場が開かれ、この富塚や藤ヶ谷に、「松戸道」、通称「なま街道」が通った。 「なま」とは「鮮魚」の事で、つまり銚子から上がった魚をナマのまま江戸に運ぶルートとして大いに栄えた。 これが、暗くなると怖い道なのに通らないわけにいかない、という経済事情と通行心理の矛盾とが合致して、怪談が多かった理由なのかな〜という気がしている。 「斬られ庚申」に現れる商人は、「いつものように通った、ある晩」に、火の玉に驚いて「庚申塔を切りつけ」ている。 この経済的な発展を頼りに、道沿いには集落や寺が移され、新田も開発されて、それまでの「村」としての仕切りが脅かされる事態にまでなった。 この事が村雨丸の伝説ができる土壌となった。 右に16号線との交差点「藤ヶ谷」が見える(パノラマ4枚180度以上)
実は「村雨丸」に出て来る「お堂」らしき物と西輪寺は、戦国時代が終わったばかりの1602年に確認できるそうだが、村雨丸父子のために書写した経を納めた事になっている「村雨山」「二部山」は、古い地図ほど確認できないという。(「むらさめ」が1628年、「急雨山」が1743年、「二部山」になると、幕末の1854年にようやく出て来るのだとか(^_^;)) にも関わらず、「西輪寺」も集落も、「村雨山から移って来た」と言い伝えられているそうだ。 そう思って見ると、若干ながら、寺の位置と山とされる位置には距離があるような……? 地図←西輪寺、地図←「村雨山・二部山」とされる場所 「伝説」が「後世作られたと見られる根拠」として、江戸時代の新興地であった「富塚」(白井市がわ)が、自分達の利益を守るために、 ①自分達の土地が古くから由緒を持つとする歴史を作った ②そのために、他の土地の人を味方に取り込もうとした ③自分達の領域が分断されないよう手を尽くした……事が見てとれるからだという。 道路に出て、向かいの駐車場から森を写す(パノラマ4枚180度以上)
(↑森の中には、8体ほどの仏像を象った石祠と、新しい和式墓が一体あるのみで、私有地という感じに思えた) 白井市には江戸時代、新たに発展した薪炭開発や金融で成功した牧士がいた。 そのように、実は新興地であった「富塚」が地主となって、古くから開発されていた南相馬の藤ヶ谷の人々を、自分達の方へ取りこみたくて、相馬にちなんだ、いかにも武家らしい伝説を、自分達の持つ太子信仰の寺(=西輪寺、太子信仰は商売繁盛を祈願された)と結びつける話を作った……というのが真相のようだ。 武士が登場する話や合戦話が誕生する理由も、その辺りにあるのかもしれない(笑)。 そう思って振り返ると、この「村雨丸」の伝説では、平胤吉は「南相馬」の人と思われるのに、この胤吉が建てたお堂(西輪寺)は、領域を越えた(今の白井市)の「富塚」方面にある事に気づく。 そして、1700年代半ば以降、この地域が開発の波にさらされ出すと、おもむろに「村雨山」の地名が現れ出すという。 「村雨丸」の伝説は、「村雨山」と後に地名づけた土地を、「最初に村が開かれた土地」と訴える手段のため、様々な証拠を作って編み出された創作と見る事ができるそうだ。 となると、怪談にも牽制の含みがあるのかもしれないし(笑)、16号線の南北に伸びる村雨丸伝説の痕跡も、「あえて南北に長く主張した」って事なのかな、と思った(^_^;)。 ただし、地名が後付という話であって、「村雨山が村域」というのは嘘じゃないのかもしれないし、「合戦など無かった」とまで言ってしまう事もできない(^_^;)。 ↓こちらは数日後、やや西の「高柳城跡」を通った時の写真。 高柳城跡も相馬岡田氏の支配領域なので、鎌倉〜室町初期の邸跡なら相馬岡田氏の遺構であろうが、戦国期の城跡のようでもあり、相馬岡田氏の手から離れた後に成立した可能性もある。 実は、高柳城のちょっと北にある「増尾城」も、相馬氏(恐らく相馬岡田氏)ゆかりの城として、教委の看板まで建っているものの、今に残る形状は戦国期の遺構に思える。(2005年10月<増尾城址公園(千葉県)>) 「増尾」は、相馬時代の城館地名にあるが、その至近距離にある「幸谷城跡」が、戦国期の要害と言うより、むしろ前時代の「邸」程度の造りである点から、こちらが相馬時代に「増尾城」と呼ばれた物か……という気もする。 しかし同じ相馬氏の守谷城のように、前時代の邸跡地を戦国期になって必要に迫られて造作し直したケースもあるし、相馬氏じゃなくても、古墳跡に城跡が建ってるケースなどよくあるから、高柳や増尾の城跡が、「鎌倉時代には用いられてなかった」とまでは断言しがたい(^_^;)。(2009年7月<北東部「守谷城跡」1、城内地区>以降) それと、幸谷城跡らしきで1485年に「佐久間氏」なるものが討死する合戦の記録があり、この高柳城跡の戦国期特有の城構えと言い、「この辺りに合戦など無かった」とまでは言い難い(^_^;)。
ネット上では、相馬岡田氏は最終的に陸奥相馬氏の家臣として、南相馬(福島県)に存続したような記述を散見する。 私も相馬に行った時に、家臣の名として見た覚えがあるし、相馬岡田氏が鎌倉〜南北朝〜室町を通して、南相馬と下総北西部の両方に所領を受け持っていた事も、確かに確認できる。 戦国期に向かうにつれて、北総部の領有からは離れて行ったようだが、ここ藤ヶ谷周辺における相馬姓の多さ、相馬伝説に対する周囲の気遣いから、室町時代の途中までは支族か代官が在地支配していたとも、江戸時代の前までに帰農したとも想像できる。 ただその間の動向については、東北と関東は室町期、鎌倉府によって束ねられていたので、やはり鎌倉府の崩壊〜古河公方五代の時代……つまり永享の乱あたりからわからなくなってしまったのではないかと思う。 以上、関連事項は(10/24遅れてリンク(^^ゞ) ■相馬御厨・相馬氏(平将門・千葉氏を含む)関連 2002年8月<増尾城跡(柏市)>(←ちょっと前から) 2005年10月<増尾城址公園(千葉県)>aおよびb 2005年11月<将門神社>内 2006年8月<泉、龍泉院>内 2007年9月<松ヶ崎城跡(柏市)>内 2008年7月<高柳城近辺(柏市)の菜の花と桜> 2008年8月<取手市「相馬惣代八幡宮」> 2008年10月<下妻市「鎌輪の宿」>内以降 〃 <取手市「延命院・神田山・将門胴塚」>内以降 2008年11月<千葉県我孫子市「龍崖城」(将門の乱・伝承地)>内 2008年12月<兵主八幡神社>以降 〃 <布瀬城跡・香取鳥見神社(天慶の乱・伝承地)>内 2009年5月<相馬・中村城跡(東〜南側)>以降 2009年6月<「柴崎城跡」の周辺「柴崎神社」(我孫子市)> 〃 <「布施城跡」と、その周辺(柏市)>内 2009年7月<西部「御霊山」>以降(守谷相馬氏の将門伝承地) 2009年8月<東光院>内 2009年9月<1日目・千葉城(亥鼻公園)>内 2009年10月<胤重寺>内以降 2009年11月<犬吠埼の夜〜朝(#^.^#)>内以降 2010年12月<将門神社(沼南「龍光院」)> 2013年11月<高柳城跡「善龍寺」、桜の残り咲き(^^)> 〃 <「イラストで知る白井の伝説」と手賀城伝説> 2014年4月<鎌ヶ谷市「相馬野馬追」騎馬武者パレード、①出陣> ■他(白井市) 2012年8月<白井七福神めぐり①大黒@「延命寺」> 2012年12月<白井市・木下街道そば「河太郎」> 2014年4月②<白井市「神々廻城跡」(鳥見神社)>内 <積雪> ここ3年ほど、2月に必ず豪雪となって、積もると冷え込みで2〜3週間は溶けない。 チャット(ピグ)では東北の人にまで、「千葉県は大変だったそうで、大丈夫でしたか」などと聞かれる始末である(笑)。
そもそもベランダに雪が積もるのを見た事がない。屋根や壁、他の建て物に阻まれて雪が入って来ないし、届いても室内の暖に溶かされやすいので、この積もりようには驚いた。。 雪は入りづらくても日は差すので、雪が降りやめば……
私も積雪の翌日は、駐車場の雪かきに精を出した(^_^A)。 千葉県では、どこも雪置き場なんて設置してないから、除雪で集められた雪はドンドン高さを増して、一時は家の高さを凌ぐほどに盛りあがる所もあった(どうやってあんなに高く乗せたんだろう笑)。 去年までは無かった除雪道具が、今年からはマンションの物置きに常備されるようになって、近所の人々と声を掛け合ったり協力しあったりなんかして、だんだん「雪かき」が、毎年の恒例行事になりつつある感じがした(苦笑)。 やはり道路より土の出ている所が雪原に(パノラマ2枚)
山梨県や東京や埼玉の奥地で、積雪量の多さで孤立化したニュースが連日聞こえてきた。 除雪作業は嫌いじゃないので、もっと雪かきに慣れて、そういう所を助けに行けたらいいなぁ〜と思った。 そのためには、除雪技術や知識・情報・連絡手段の取得も重要だが、何より大事なのは体力だろう。 ここ2〜3年、体調不調ぎみなので、加齢も気にして体力づくりを心掛けるようになった。 ……と言っても、週一回の運動の他は毎日歩くだけだが(^_^;)ゞ 、千円そこそこの靴はやめて、五千円以上するが、持ちが良く歩きやすい運動靴を履いて歩くようにしたら、30分でヘロヘロだった足も、1時間ぐらい平気で歩けるようになった(゚.゚)! 今年は二年目なので、「もう一足買いましょうo(^^)o」と、履き替え用も揃えた所なので、少し力がついてきたかもしれない♪ 稔台の「東京靴流通センター」(地図)のが一番かなぁ☆ミ(松戸って昔からイイ靴屋が少ないのよ。。) 「健康は足からだけど、雪かきには握力も必要よね」 と思い(握力スゲエ無いッス汗)ながら、ふと寄った店の陳列ラックで……↓ 並んだハンドグリッパーが何気に凄すぎる件(・・;)。。(汗&爆)
余裕かまし過ぎ→→→激辛食い過ぎ みたいな移り変わりが楽しいですね(笑) 除雪スコップを持つ手から、思わず力が抜けそ(^^;)。。 <「は〜るが来〜た(^O^)」・梅花・菜の花> 何とか雪も溶けて、梅や菜の花が咲き始め、ジワジワと春に向かう気配(#^.^#)。
「菜の花だー(^O^)」とカメラのシャッターを押したら、ちょうど後ろに黒い車が通って、黄色が一層きわだって写せた☆ミ
さっきの高柳城の近くのレストランの窓から(パノラマ2枚)
レストランが出来たのは、つい最近……この春ぐらいからだったかなぁ〜。 地図←「モモンガ」というサンドイッチとパスタ専門のお店。グーグルの写真にまだ載ってないね(^^ゞ。 この高柳は、ちょっと西にいくと藤心の「アンチーブ」(地図)もある。 今までこういうお店が殆ど無かったけど、田園や河辺を一面に見渡せて風光明媚なので、こういうお店がドンドン出来ると嬉しい(^^)。<貧乏だから、あまり多くは来れないけど さて、しばし梅の花をお届け(^^)
↑しいの木台か六高台あたりだったかと(^^ゞ。 お次のはハッキリ記憶。いつも通る、逆井の梅林(地図)↓ いつ見てもここの梅花は綺麗だなぁ。空の色との兼ね合いもいいし
安倍蚤糞のせいか、この頃は飲食店(喫茶店やレストラン)が出来るのを見るし、そこそこ人が訪れているようで、一見好景気に見えるが、これも安倍蚤糞と同じで内実は数字合わせの誤魔化しが濃厚で(笑)、スーパーなどが出来るたび、激安合戦が展開されてる。つまり実は前よりデフレ傾向(助かってるからいいけど笑)。 それとよく見ると、飲食系のお店というのは、大抵は介護施設と一体だったり、自然食やデリバリ食など、お年寄り向けが多い(^_^;)。<いわゆる公共事業景気ですね(笑) 道路と反対側(梅林の裏手)に廻ると、今度は白梅の勢ぞろい(^^)
ここも立派な介護施設があるんだけど、さっき言った藤心の広い田園地帯にも、このほど二階建の介護施設が建って、はじめて視界を阻む物が現れた。 こうした介護関係の建て物が、ここ数年ドンドン増えている。 お年寄り向けのサービスが増える事自体は、悪くないと思うけどね。(民主党政策の名残りにせよwww) よく若い人に住んで貰わないと云々……と言うけど、誰でもいつかは年を取るんだから、住んだ場所で老後が暮らしやすいとか先々が安心と思えば、若い人も住まなくないでしょ(^^ゞ。 以上、関連事項は(10/24遅れてリンク(^^ゞ) ■逆井の梅林 2006年8月<まずは逆井の梅から(^^ゞ> 2007年7月<逆井〜手賀沼・栗ヶ沢> 2008年7月<逆井の梅花〜手賀沼(柏市)> 2011年10月<初春の手賀沼・古利根川> 2012年8月<梅の開花がすごく遅かった件> 2013年10月<黄砂と梅花> <手賀城址①「興福院」> ↑千葉に来て車買って、手賀沼に来るようになってから間もない頃、「手賀城」を探して、沼南をウロついた覚えがある。 手賀沼の事を最初に「たわごと」でレポしたのは、将門神社だった。探すと、「2004年11月」と言ってるレポが、2005年11月号にある。 その後、2006年8月号で、同年3月ぐらいのレポをしながら、「城山聖地公苑」を指して、「“城”とは手賀城の事じゃないか」っぽい事を言ってるので、この時は既に行ってみた後なんだろう。(2006年8月<手賀沼>内) でも、そのときのレポで地図が差している位置に今あるのは「柏湖南聖地公苑」(地図)なのよ(^_^;)。 もっとも地図は後からマップファンのに付け替えたので、その時ズレが生じたのでなければ、公苑の名が変わってる事になる。 しかも、このほど、正確な位置を割り出して行ってみた所、手賀城跡がある位置に近い墓苑と言えば、「平和公園共同墓地」(地図)じゃないかな、と思うワケ(^_^;)。……ま、いいんだけどね(笑) 手賀城は城域が広く、支配者として伝わる「手賀原氏」に関する伝承は、さらに広範囲に広がっている事から、かなりの勢力を持っていた事が推測される。
山門の左脇には、 「沼南の歴史をあるく 1 興福院・手賀城跡」 という標が建っていて、その側面に、
「手賀城らしき痕跡に初めて出会ったねぇ(^^)」と、梅の咲く晴れた春空の下、思わず笑顔になった☆ミ
和歌には……
この反対側、本堂に向かって右には、「力石」と「手賀ばやし」の看板がある。
「おはやし・ニンバ・ショウゼン・カマクラ・シチョウメン」と5囃子あり、境内での神事の後、神輿・山車が兵主(ひょうず)八幡神社(2008年12月<兵主八幡神社>)に向かい、行き帰りの各所で演奏される。 まず「おはやし」でシシとキツネが踊られ、「三番叟」で翁が剣と鈴、黒式尉が剣と扇で悪を追い払い、「式三番」の祝いの舞で作男が袂で福を掬い上げ、「ニンバ」でひょっとこ・岡目がリズミカルに踊る。「カマクラ」はゆっくりテンポに、シシが眠りにつく時に演奏される。
その四面を見渡すと、「無間地獄、衆生の重罪、百病の苦しみ、極楽にある八功徳水の蓮池、長寿や招福」などの字面が見られ、本堂に前進すると、十一面観音像と、その頭上に蓮花を象った屋根瓦(鬼瓦)が見える。 蓮はこんにちも手賀沼の水面を蓋って、夏にはピンクの花を多く咲かせるが、大抵こういう場における「蓮」は、水害供養の意味合いが含まれている事が多いだろう。 この寺の号も「竜猛山」と、大水害の存在を匂わせ、いかにもすぐ近くに手賀沼が迫っている事を感じさせられる。
この観音像は、もしかすると、「手賀城の女城主」がイメージされてるのだろうか(^^)。 2013年11月号の<「イラストで知る白井の伝説」と手賀城伝説>内で、白井市の小森城主が、柏市の手賀城の女城主に恋をする伝説を書いた。 ここが本当の手賀城跡なので、もう一度書いておこう(^o^) 「板ばさみの小森城主」 昔、平塚の小森に城があった。小森の殿様は千葉氏の家来で、ある時、沼の向こう岸にある手賀城の攻略を任された。 しかし、小森の殿様は、あれこれ理由をつけては攻めこまずにいた。 と言うのも、敵の手賀の殿様は、実はたいそうかしこく美しいお姫様で、小森の殿様はこの姫に恋をしていたからだった。 人知れず夜の手賀沼へ船を浮かべ来る女城主の姿を小森の岸辺からいつも見守っていた。
主の命令とは言え、攻めるに攻められず、毎日思案していたが、たびかさなる命令も断わりきれず、援軍がくるという話になって、板ばさみとなった小森城主は、手賀沼に身を投げて自殺してしまった。 現地の大将を失った千葉軍は、結局手賀城を攻め落とすことができなかったという。 以上、主人公が敵と味方(身内や主君)との板挟みとなって、身を投げて自殺してしまう結末が、先ほどの「村雨丸」と似ているが、この小森城主の話も、江戸期の創作と言われている。 以前も話した通り、心中や仇討ちといった筋立ては、江戸期の庶民に受けた。 例の佐倉宗吾の話にも、宗吾を江戸に送りだすため、禁を犯して船を出した後、印旛沼に身を投げる船頭の話がある。 栃木の塩原に行った時も、小太郎ヶ淵で、父の仇と、仇の娘との恋の狭間で懊悩のあげく、川に身を投げて死んでしまう小山小太郎の話があった。 小森城と手賀城の「城主同志の恋」の設定は、これもやはり、小森城跡のある平塚地区にある東光院や延命寺が、江戸時代にはここ興福院の末寺であったので、対岸にある手賀城に「実は愛情を持っていた」と創作して伝承したという(笑)。
お墓の傍らにある石碑には、漢文がビッチリと刻み込まれていた。手賀村の戸長さん「染谷氏」の事蹟を綴った物のようだ。 白文だし、所々に字の摩耗もあって、全部読めたわけじゃないが……。 最後の将軍・徳川慶喜の大政奉還の後、明治の世となり、政権が一新されて廃藩置県となり、町村合併などもあって改めて選出された戸長の染谷さんが、大変に善人で、すこぶる公平に職に努めたので、庶民が喜んで服し暮らした事、職を辞した後は和歌や茶を楽しむ日々を過ごした事、名声を引き継ぐ子孫が絶えてしまい、功績を伝える者が居なくなった(か居なくなる事を恐れた)ので、碑を建てた……。 というような事が書いてあるんだと思う(今イチ自信が無いが(^_^;))。 幕府が倒れた後の東京とその周辺(特に幕府の直轄地)は、よく伝えられる明治の新都市然とした風景になるまでの間、相当に廃れたとか治安が悪くなったと聞く事がある。 そのたびに、一定の権力者とそれに伴う行政期間が無くなった後も、一定の秩序を保った所は、こういう地元のまとめ役的な人の人望なり努力なりが、ずいぶん底力を発揮したんだろうな〜と思う。
明るすぎず暗すぎず、広すぎず狭すぎず、暑すぎず寒すぎず、適度に湿って乾いて、実に良いムードだった(#^.^#)。 ところで、さっきの伝説にいう「小森城」、誰の城でどういう勢力に属したか皆目わからないのだが、それ以上に謎が残るのが、この話における千葉氏と原氏の関係(^_^;)。。 「実は愛していた」なんて設定を持ち込むのも、そもそも「敵対関係だった」と伝わっていたから、言い訳の必要があったわけだ(^_^;)。じゃあ、その「敵対関係」とは何ぞや(笑)。 原氏と戦闘した千葉氏と言えば、私の知る限り、市川合戦で滅んだ千葉宗家だが、いっぺんで滅んでるので(^_^;)、あとはその後裔で、上杉を頼って房総から出て行った武蔵千葉氏が原氏の敵対勢力にはなるだろう。 ……が、エリア(距離)的に無理があるような気が……(^^;)。。
小森城主の話の翌回、2014年1月号(2013年12月号は欠番)の<小森城跡・名内城跡と「手賀合戦」>では、実際に小森城跡に行き、手賀城にいたと思われる「手賀原氏」について書いた。 これも繰り返しになるが、ここが本拠地なので、もう一度書いておこう。 「手賀合戦」とは、「東国戦記実録」(近世に書かれた戦記)によると……。 1579年に千葉国胤が弟の頼胤を大将とし、原胤栄を先陣として白井を攻めた。千葉富胤の子で原氏に養子に入った小林の原氏も与した。 手賀原胤親は驚いて、防戦のため「名内ノ台」に陣し(実際そこに名内城跡(地図)がある)、これに我孫子氏・小金の高城氏・芝原中峠の河村氏・布川の豊島氏などが加勢して、300余が立てこもった。 が、国胤の発病で引き分けとなった……という(^^ゞ。これを「手賀合戦」と呼ぶそうだ。 この伝説も史実的にどうなのか確認できない(^_^;) 「国胤」は佐倉千葉氏の「邦胤」の事だろうが、原氏については、本家「胤栄」と手賀原氏の「胤親」の対立構図は、二人が兄弟という説に乗っていると思われる。 ところが、この「胤親」なるは戦記や寺伝に、存在自体が創出されてる可能性があるそうだ(^_^;)。 ↑墓地と本堂の間の坂を下りて来た(パノラマ5枚180度以上)
振り返ると、こんな青々とした竹林が(^^)(パノラマ5枚180度以上)
同じ「東国戦記実録」あるいは「東国戦記」と呼ばれる書物に、「印西合戦」が書かれている。 内容は、1575年、茨城県の牛久の岡見氏の家来、栗林義長が印西(手賀沼の東隣)を攻撃し、小林城の原氏父子が千葉方の武士とともに防戦した、というもので、同様の物が「常総軍記」にもあって、こちらでは1585年の戦いになっている。 前に牛久城に行った事がある。 年代はハッキリしなかったが、佐竹(旧・関東管領上杉)勢力×後北条(旧・古河公方)勢力の衝突ラインにあり、牛久の岡見氏は後者勢力として、千葉県の豊島・高城の同盟を得て城を守った……と書かれてあった。 ちなみに、前者勢力としては多賀谷氏の存在がある事もその時に書いた。(2008年7月<牛久城跡、2>内) この「印西合戦」については、印西市教育委員会の本に、「(対する北総地域は)既に後北条氏の傘下にあって、戦闘が起きたとは思えない」と記されていた。 つまり江戸時代の空想物語らしい(^_^;)。。 では、同じ書物に書かれた「手賀合戦」の信ぴょう性はどうなのか……↓ <手賀城址②「大杉神社・御神田」> 興福院を出ると、亭主が「城跡に行けるみたいだよ」と、ナビか何か見て道を探してくれたので、行ってみた。地図
で、「手賀合戦」についてだが、合戦の有る無しになると、地域や書物によってバラバラな感じがする(^_^;)ゞ。 一方に「同族間の抗争すなわち戦闘らしきがあった」とする伝説がそのまま書かれてる物を見るかと思えば、他方、「印西合戦」でも言ったように、「戦闘が起きたとは信用できない」的な論調も見掛ける……(^_^;)。。 ただ、何もかもが嘘で史料的価値が皆無というのではなく、「原氏の城跡があった」という伝承が、書かれた当時に残ってたのは確かな事だろう……という感じに、各地域の歴史認識として大まか一致してる感触を得ている。 相当するのが、この「手賀城跡」かと思え、あれこれ調べる中では、「手賀原氏」と呼ばれる一族の城であったと考えられる(^_^A)。 ただし、これと本家の原氏との関係というのが、はなはだ不透明である。。。 奥にいくほどパパーッと拓けた田園が(^O^)(パノラマ3枚ほぼ180度)
まずは本家の原氏についてだが、原氏といえば、「千葉常胤の大伯父(祖父・常兼の弟)から始まった家系」に以下の流れがある。 千葉常永−┬−常兼−−常重−−常胤(千葉氏) | └常宗(原氏) 千葉常胤は、鎌倉幕府創立の頃に頼朝を援けて、代々の悲願であった相馬御厨の下司職をモノとする事に成功した、千葉氏においてもっとも名のある人物である。千葉市の千葉城前にも、馬上の銅像がある(^^)。 その大伯父から出た「原氏」も後世に続いたようだが、大抵この手賀原氏の時代になると、この古い時代に枝分かれした一族が持ち出される話を見た事がない(^_^;)。(候補に入れる分にはいいのかもしれないが)
↑つまりこの田んぼ自体が、「大杉神社」の物という事だね(゚.゚)。 ここに来た時には気付かなかったけど、さっきの興福院で「手賀ばやし」の所に、お囃子と祭りが「アンバサマ」と呼ばれて、古くから親しまれ信仰を集めたように書かれていた。 「アンバサマ」というのは、「大杉神社」の神様の呼称(^^)。 大杉神社は茨城南部にある、このあたりでは有名な神社。ちょくちょく勧請された支社を見掛ける。 この「たわごと」では、「千葉県の動乱」で、1455年に千葉宗家を急襲して滅ぼし、その子孫(武蔵千葉氏)を武蔵に駆逐(市河合戦)してしまう勢力として、千葉宗家から分かれた「馬加氏」と、この馬加氏と結託する「原氏」の存在を語ってきた。 (2008年7月「千葉県の動乱」<武蔵千葉氏×馬加氏「市川合戦」(1455〜1456)>)
この室町時代に下剋上の色合い濃厚に現れる「原氏」は、室町期、新たに千葉宗家より分出した支族のようだ。 系譜の出自には若干の違いもあるようだが(^_^;)、私が書籍で確認した系図だと……、 <千葉> 氏胤┬満胤┬兼胤−胤直(市河合戦で滅ぶ) | └康胤(馬加)┬胤持 | └輔胤 | ↓ ├重胤(馬場)…胤依…輔胤−(佐倉)孝胤−勝胤−昌胤−胤富(海上)−邦胤−重胤 └胤高(原)−胤親−胤房┬胤隆−胤清−胤貞┬胤栄 └胤宣(手賀原?) └胤親? 千葉氏胤は南北朝時代、満胤は室町初期の人。どちらも千葉宗家、つまり千葉氏の惣領だ。 あと、原氏の初代「胤高」が、「満胤の弟か子」という違いがある系図もあるようだ(^_^A)。 本殿の左脇(北西)。平地の向こうに手賀川がある辺り(パノラマ5枚180度以上)
明治時代の地形図で、古くは水位がここまで迫ってたそうだから、この城から直下に、昔は手賀沼の水が迫るのが見えたんだろう。 この位置は、いつも手賀川の土手脇を通るルートから見えるし、手賀川は地図で見る限り、手賀沼の東側を、その南北から埋め立ててて細めたような感じだからね(^^ゞ。 この城の機能してた頃には、船舶との繋がりがあった事が想像され、それで江戸期の話で、「女城主が湖上に舟を浮かべ」それに乗っている様子が描かれたのだろう。 こんな風に、作り話の中にも今は失われた風景が現れ出る事はあるので、創作だからと何もかも否定して抹殺(腐った歴オタ歴女と、そいつらを振り回してる、ここ30年程度のパッと出な学者に、この傾向が強い)すればいいわけではない。 さらに、本殿の真裏(北)に廻る(パノラマ5枚180度以上)
胤高の孫・胤房が千葉宗家に謀叛して滅亡させた、いわゆる市河合戦(これは史実よ(^_^;))の後、その子・胤隆は、小弓義明を担ぎ出した真里谷武田氏との抗争に敗れ、小弓城を取られて、北相馬(茨城県利根町布川)で没した。 その子・胤清になると、北条氏綱の支援を得て、小弓城を回復した。 (「千葉県の動乱」<武蔵千葉氏×馬加氏「市川合戦」(1455〜1456)>)
「手賀城主原氏系図」なるにも、「原胤貞が手賀を賜わり、後に筑前守・胤親が続いた」とあるので、「胤親」を「胤貞の子」とするように思える。 <さっきの系図から原氏のみ抜粋> └胤高(原)−胤親−胤房┬胤隆−胤清−胤貞┬胤栄 └胤宣(手賀原?) └胤親? しかしどうもこの名は、室町期の原氏・初代の胤高の子が「胤親」である事からの後付と見れるらしい(^_^;)。 それよりも、真里谷武田氏や小弓公方・義明との攻防に敗れ、手賀の東、利根町布川で没した胤隆の弟に、胤宣というのがいて、これが本土寺過去帳(当時史料)において、「手賀の原出雲守」と書かれているらしいから、むしろこの系統の子孫ではないか……とする説がある。 以上をもって、2014年1月<小森城跡・名内城跡と「手賀合戦」>の再提示は終了。あとは見るだけ(^^)。
「東国戦記」の「手賀合戦」があったかどうかは、「原胤栄」と「原胤親」が同時代に無ければ成立しないから、この点が崩れてしまった場合は、「疑わしい」という事になってしまうが、一つ気になる事がある。 先ほどの小森城主の話で、「小森城」が、「手賀城と敵対関係にあった」「千葉氏から援軍が来る(間柄だった)」という前提があった事を受けて、二つの地域を親和的に補正するべく、「女城主に恋」が出て来た。 すると小森城には、「胤栄」か、「胤栄側」の勢力が在城していた事になる……と、少なくても江戸時代には「受け取られていた」事になる。 これは、一度「(原氏同志に)合戦があった」と創作された話を、「地域の歴史」と土地が信じた頃があったから……という事にはなりそうな気がする。 これより下に降りて、周囲から遠望したり、崖下から見上げてみよう(^^)
今いた「手賀城址」の石碑があった「神社」(大杉神社・御神田)の高台がこのように遠望できる(^^)。 ただ、手賀沼に車で来るようになったばかりの頃は、確かこんな感じではなかったのが、後でこのように整備されたような記憶がある。 前は確か、もっと手賀沼の中央寄りの墓苑に「城山」と名付けられ、自分もそこに入って「城跡らしき痕跡が無い(゚.゚)」と思ったので、かつては、「城」と思われる(伝承される?)位置が、もうちょっと広範囲だったのかもしれない(^^ゞ。
なるべく真下に貼り付いて撮影を試みる(^_^;)(パノラマ3枚ほぼ180度)
実は、この飛び出た高台の左隣(東側)の敷地に墓地があるらしく、そこを虎口と考え、さらに東に城跡の東端部分があって一度途絶え、さらに東隣に今は「平和公園共同墓地」(地図)があるわけだが、その間に今は道(地図)がある。 この道部分、手賀川からほぼ垂直に水を引いて来たように伸びて来ている。 この道にかつては水路があり、手賀城と水路を隔てて東側(今は「平和公園共同墓地」のある側)に船戸と称する島地があって、水路に船を隠し置いたのではないか……という仮説がある。 これは、ここ手賀城がこのように水辺から見えるほど高く、しかも水辺にむかって飛び出ているため、水域から見ると目立ってしまう地形に対し、この突端部分がむしろ障壁となって見えない奥まった水域に船団を準備しておけた……という事になる。 かつての地形っぽくウネリを見せる(パノラマ3枚ほぼ180度)
江戸期だと、現在ほど乾ききった陸地つづきになりきってなかっただろうから、もうちょっとかつての面影に近かったのかもしれない。 すると、「女城主が船を浮かべて湖に出て……」などという、今聞くと突飛に思える図も、もしかしたら「ここから舟を出せた」という様子を、今よりは容易に想像できたからなのかなぁ(^^ゞ。 以上、関連事項は(10/24遅れてリンク(^^ゞ) 2006年8月<手賀沼>内 2008年7月<牛久城跡、2>内 2008年7月「千葉県の動乱」<武蔵千葉氏×馬加氏「市川合戦」(1455〜1456)> 2008年12月<兵主八幡神社> 2013年11月<「イラストで知る白井の伝説」と手賀城伝説>内 2014年1月<小森城跡・名内城跡と「手賀合戦」> ■手賀沼(長くなったんでリンクページ作った↓) 「手賀沼の史跡」「手賀沼・手賀川・下手賀沼」 ■3月・茨城県水戸市・常陸太田市・北茨城市・笠間市 <水戸・茨城県立歴史館「常陸南北朝史」展> 全部で……5回ぐらいで行けるかなぁ。 恒例・年一旅行だが、前回から経済的に苦しくなった上、今回からさらに経費節約に切り替えた(安倍蚤糞を支持しません藁)ので、年一から速度を落とした。 それで、いつもなら秋に行くのを、ジワリ遅らせて翌春に廻した。 場所もさらに近場を設定。 茨城県(爆)。ま、一応「旅行」だから、ちょくちょく行ってる南部および中部(下妻・鹿島・下館など)ではなく、ちょっと遠い北部に焦点を絞った。 それが↑にもある通りの地域。水戸以北とでも言うかな。 茨城県は、西部は栃木と接して北から凹まされているが、東部はむしろ北に突き出て、東北(福島県)と接している。
このSAは守谷だったかな。 高速は常磐道。そう遠くない所だと乗らないが、水戸(地図)となると流石にちょっと遠かったわね(^_^;)。 もっとも2度目3度目といく場所だと、だんだん「意外と近い(゚.゚)?」と驚く事が多いから、初めて行く場所で遠く感じたというのもあるかもしれない。 千葉・東京に住んでて、水戸に行くのが初めてというのは、もっと遠隔地の人には意外に聞こえるかもしれない。 水戸は中高生の頃、1〜2度行った事があるはずだが、なぜか記憶に乏しく(^_^;)、本格的な旅行として行ったわけではなかった気がする。 結婚後、千葉に来てからも、栃木や福島内陸部、茨城南部にはよく行ったが、茨城北部〜福島沿岸部には殆ど行った事が無かった。 だからどんな旅行になるのか、全くイメージが湧かなかった(^^ゞ。 これは前回の群馬旅行でも、同じような感じだったけどね(笑)。 まだ「土浦北」を目指してる辺りっぽい(^^ゞ
あいにくの雨……それもかなり土砂降りだった。。 この日は一日こんな具合だったけど、翌日から晴れて、良い風景がたくさん見れたよ(^^)。 途中、茨城県の観光マップが出ていて、見たけれど、水戸より海岸寄りで、佐竹より南に「武田氏館跡」というのがあった。 現在は、「甲斐武田氏発祥の地」として整備しているようで、出ている写真には、館っぽい建物が作られてあるようだ(゚.゚)。(武田氏館@ひたちなか市HPより)(武田氏館@裏辺研究所より) 武田と言うより……佐竹と言うべき感じもするけど(笑)。 それで言えば常陸国は、他にも、平家一門や伊達氏や藤原氏の発祥地でもあるんじゃないかなぁ〜(^_^;)ゞ。全部作らないと(爆) 水戸に着くと、最初に向かったのは「茨城県立歴史館」(地図)。水戸のほぼ中心地にある。 敷地に入ると、まず目に入るのは……、
博物館はこの右→にある。 これね。「茨城県立歴史館」(パノラマ2枚)
この時期は「常陸南北朝史」という特別展をやっていた。 これが……なかなか良かった(^o^)☆ミ ちょうど茨城県に行ってみようという機運が盛り上がって来たのも、室町期の北関東の歴史がだんだん飲み込めて来て、ここらでいっちょ……という気分になった所だからだ。 この展示会で、歴史的にもボリュームを持って関東最大の結節点となった南北朝動乱に触れられた事は、すこぶる成果が高かった。 亭主が私以上に熱心に一展、一展に見入っていて、ちょっと驚いた(゚.゚)! 私らだけでなく、他の見学者にも、見学者同志で歴史の話をしていたり、係員に歴史の質問をしたり、じっくりと説明を読んで進むなど、わりと歴史に熱心な人が多かった気がする。
ここでは偕楽園・弘道館を世界遺産にする運動が、他では斉昭の大河ドラマ化推進運動が展開されてた(笑)。 館内のトイレに入ったら、個室のドア内側に、「喫茶コーナーのご案内」が貼られていて、メニューの中に「徳川将軍珈琲 300円」というのがあった( ̄▽ ̄;)。 これ、ウチの方でも、徳川慶喜珈琲というのを見た事があるんだけど、ブランド名から、同じ物じゃないかと思う。 私はこれを、松戸の21世紀森と広場の近くの喫茶店(2011年9月<松戸市「祖光院」「カフェ・リビエラ」「庄や」>内)のメニューで見た(^^ゞ。 松戸には慶喜の別荘「戸定邸」があるからだけど、何でも慶喜が公式にコーヒーを導入した記録から、作られたブランドだったと思う→「サザコーヒー、15代将軍が飲んだコーヒーを再現」 慶喜は水戸出身だから、当然本場のここでも飲まれているんだね(^^)。
特別展の後、二階の常設展を見学したのだが、特別展で疲れて常設の方は適当に見流すのかと思ったら、そこでも尚一層、亭主が熱心に読み込んで、あげく、 「いつも城主(私)に聞かされたり、「たわごと」で読む事がいっぱい出てて驚いた! すごく読み込んでしまった!」と、こちらも驚きをもって言っていた(笑)。 ただ、さすがに歴史事項が盛りだくさんで、その調子で見学してたら時間がかかって、実はこの旅行、ここで予定が大幅に遅れて、1日づつ後ろにズレ込んだので、予約した宿泊所との兼ね合いがちょっと変な具合になった(^_^;)。
展示類は以下に書く物だけじゃないんだが、あくまで個人的な感想で……。 まずは夜刀神とか常陸風土記とか、常陸の名で全国的に有名な古代史から始まって、平将門の乱も大きく取り上げられていた。 個人的にはこの後にいく、佐竹氏関連の歴史に注意を払っていたら、鎌倉時代の所で特によく取り上げていたので、後で受付で展示解説書籍を買った(#^.^#)<ホクホク☆ミ 南北朝史は、もちろん北畠親房の戦歴が多く語られているが、意外なのは南北朝時代だけに留まらず、下総・常陸においては、室町時代の鎌倉府を取り巻くイザコザも、全て南北朝動乱と連続して取り扱われていた。 小山氏の乱や、小栗氏の乱、小山氏遺児を匿った事から、鎌倉府からの追求が、常陸大掾氏にまで及んだ歴史が詳細に連ねられていた。 そして上杉禅秀の館跡から発掘された、数々の出土(茶器の破片)が展示されていたのには、思わず「おおっ!」と、鋭い声が出てしまった(^_^;)ゞ。。 だって、水戸で見られると思ってなかったんだモン(笑)。 ……最後に、「茨城」は、「いばらき」と読む。「き」に濁点をつけないのが正称である(笑)。 <水戸市街と水戸城「彰考館」跡> 「茨城県立歴史館」の敷地の向かいが、有名な「偕楽園」だが、県庁所在地のある大都会(千葉市とか仙台市とか)によくある如く、道路事情が難解だったりして(笑)、変な方向に迷い込んだりしたあげく、やっと「偕楽園」に到着。 「あやうく偕楽園で遭難するトコだったね(^_^A)」(爆) とか言いながら入った駐車場が有料だったんだが……、 僅かここまで歩いて来ただけで、雨ザーザーがスゴすぎて(・・;)、梅園を見て歩く事とこの日の予定をだいぶ押してた不安が一気に重なって来て、 「駐車場料金が無駄になって申し訳ないけど、偕楽園は後に廻した方がいいと思う(^_^;)」 と提案。 亭主も同意してくれ、駐車場に戻って、 「スイマセン、急用が出来て、今来た所ですが……(^_^;)」 とダメ元で事情を話してみた所……ナント、 「ああ、それならいいですよ(^^ゞ」 と、すぐ料金を返してくれた(゚.゚)! 「スゴイ親切(≧▽≦)!」 「水戸黄門は庶民の味方!」 貧乏夫婦は大喜びで、駐車場の係の人に御礼を言い、頭を下げながら去った。 (好印象だったので、偕楽園には最終日の最後の見学に再びやってきた(^^)v)
水戸はやはり偕楽園が有名だし、偕楽園の梅庭園は徳川斉昭の案(食用に出来て飢饉への備えになるし、花が咲けば民衆と楽しみを分かち合える、という事だろう)なだけあって、市内の橋などには、梅花の咲いた枝を透かし彫り風にあしらった欄干などが見られ、偕楽園の梅は全市あげての郷土自慢と思えた(^^)。
現在の水戸城址は、周囲に幼稚園・小学校・中学校・高校と、さすが「水戸学の後継地」と言わんばかりに、多くのそれぞれ大きな教育施設が建ち並んでおり、辺りは清々しい空気に包まれ、城は無くなったが、静かな佇まいがむしろ大都会から一線を画して好印象(^^)。 敷地は水戸市立第二中学校。こんな学校通える子は羨ましいなぁ(^^)。 水戸城は1100年代ごろ、馬場資幹が、今の県立水戸第一高校(地図)の付近に館を構えた事に始まるとされている。 この馬場氏を、現地では「地域の豪族」としている。 「馬場」では見付からなかったが、「資幹」だと、自前の常陸平氏の系図で、「大掾氏」から出た「吉田氏」の系譜に現れる(正確には、大掾→吉田→石川→大掾)。国香流平氏系図 水戸城は馬場氏の後、江戸氏、佐竹氏と代わり、江戸時代、家康の五男・信吉を城主と定めたが、早世したため、十男・頼宜を6年ほど駿府に入れた後、慶長14年(1609)に十一男・頼房を水戸に入れ、水戸藩の初代藩主とした。 水戸徳川氏は徳川御三家として幕府を支える傍ら、水戸を治めて明治を迎えた。 (ただ水戸徳川氏は歴代、江戸城詰めが続いたため、水戸にいる事は無かったらしいけどね(^_^;))
歩行用の門の傍らに建つ石碑が、「大日本史編纂之地」で、これは二代藩主・光圀(黄門サマ)の始めた歴史書「大日本史」作りの大事業を指し、当初は江戸の小石川藩邸で行なったが、元禄11年(1698)に水戸城に移した。 編集を行ったここには、光圀の隠居後に移され、寛文12年(1672)に「彰考館」と名付けられた。 これは「歴史をはっきりさせて、これからの人の歩む道を考える」という意味である。 以後、澹泊齋・安積覚・十竹・佐々宗淳・翠軒・立原萬・幽谷・藤田一正・天功・豊田亮栗里・栗田寛など、著名な人が関わり、廃藩置県となった明治4年(1871)までの173年間ここに置かれ、事業の完成を見たのは、発足から実に250年後の明治39年(1906)だった。
この「二の丸展示館」はわりと真新しく、散歩中の市民が立ち寄っても良さそうな感じ(^^)。 グーグルの写真では、この辺りにはまだ工事中の画像が出てるから、最近出来たのだろう。 中に入ってみると、水戸城だった頃の歴史などがパネル展示で紹介され、早速「烈公(斉昭)を大河ドラマに!」の推進運動をしてる様子が伝わって来た(笑)。 二中の子達がんばれっ!\(^O^)/ 時間が無いので、見学はここまでにして、水戸二中と水戸三高の間の道を東に進み……↓
水戸城の全体の敷地は(地図の詳細は各々拡大して見てね)、東から「下の丸」「本丸」がこの県立水戸第一高校(地図)、「二の丸」が今までいた、水戸市立第二中学校(地図)、県立水戸第三高等学校(地図)、茨城大学附属小学校(地図)、「三の丸」が「弘道館」(地図)、水戸市立三の丸小学校(地図)、県庁三の丸庁舎他(地図)の4区画から成る。 水戸城は石垣のない平山城としては国内最大級で、御三家の居城にふさわしい名城だっただろう。 戦後に建てられた学校郡の中にも、本丸・二の丸・三の丸には巨大な土塁と堀があり、江戸時代の面影を伝えているそうだ。 <常陸太田市「大甕神社」へ> これより水戸を離れて北上するが、その後、最初の一ヶ所だけ太平洋側、すなわち東に向かう。 (そのさらに後は、さらに緯度は北上するが、方向は内陸部すなわち西に向かう)
この常陸南太田ICは、翌日も(もしかして翌々日も)使う、この旅行の結節点で、この時は北東方面の海岸近くを目指したが、翌日は西に向かうルートとして通った。 翌々日はどう行ったか、正確には思い出せないが(笑)、南西の水戸方面に戻るのにまた通った気がする(^^ゞ。 何となく風景も気にいって、その後もちょくちょく思い出すルートである。 こうやって写真で見ると、何と言う事もない道なんだが(笑)、思い出に載せておきたい。
この日たまたま、かなりの雨だったからなのだろうが、雲の様子が凄くて(写真で見るとそれほどでもないが)、山形県に行った時の、山形→東根(13号線)→新庄(47号線・最上峡)→松川温泉のルートを思い出した。 この時は豪雨の影響としか思ってなかったが、この後、さらに北に行くにつれ、さすが直接繋がってるだけあって、この辺りは何となく東北に空気(景色というか)が近いんだな〜と、後で思った。 ……で、この日、最後の見学(参拝)地は、ここ……、
↑「大甕(おおみか)倭文(しず)」と読む。 この鳥居の大きさ、大道路(6号線・陸前浜街道)に面してる向き、そしてすぐ近くに「大みか神社入口」と交差点名がついてる点からだと、ここが正面に思える。 が、入るとこの通り、やや塞ぐように建物がある。 一階には受付があるから、社務所に思われるが、中には集会所らしき広さがあって、祭りや祈祷も執り行われるのだろうが、「儀式殿」とあったから、七五三や成人式、いや結婚式ぐらい挙げられそうに思えた。 鳥居の写真を撮っていたら、建物近くにいた亭主が、神社の方と出会って話をしたようで、私を呼びに来たので、私もご挨拶をして、受付を開けて頂き、しおりを頂く事が出来た(^o^)v☆ミ やや奥まった先の方に……↓
種を明かすと、この裏背に本殿の敷地があって(次回続きをやる予定だが)、そこの「宿魂石」に閉じ込められている星の神、「天香香背男」神を、まずここで祀っているんじゃないかな……。 荒ぶる神様のようだから、祠も赤くてそれっぽい(^^)。 ずいぶん暗い中で撮ってるように見えるが、実は、本殿の方に先に入ったから、そっちの写真は若干明るい(^^ゞ。 てなわけで、次回は、まずこの「大甕倭文神社」の続きから入って、一日目の宿泊地、横川温泉に向かい一泊。 2日目を迎えて、金砂城跡と金砂神社、花園神社と、鎌倉期の佐竹氏の攻防と伝承世界をやりたい(^^)。 2014年06月30日 (スイマセン、ちょっと時間過ぎちゃったけど6月で行かせて貰うね(笑)。関連リンクは例によってまた後日) 出来ました(^^ゞ↓ 以上、関連事項は(10/24遅れてリンク(^^ゞ) 2005年11月<鹿島神宮>内 2008年4月<香取神宮・1、「要石」>内 2008年5月<香取神宮・2、「本殿」>内 (水戸旅行に入る前のレポ分も、該当箇所の最後に貼ってあります〜☆) <つづく> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|